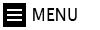
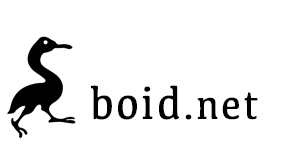

現在公開中の『MADE IN YAMATO』。シネ・ヌーヴォにて6月7日に行われた宮崎大祐監督とライターのスズキナオさんの対談の一部を特別に公開!
初対面ながら和やかな雰囲気で、映画の舞台となる大和、宮崎監督が描く二人の女性、そして日常から新たな地平を見出す宮崎監督とスズキさんの共通の視点まで話は展開してゆきました。この作品をきっかけにスズキさんが大和市を訪れる日も近そうです!
『MADE IN YAMATO』K’s cinema、名古屋シネマテーク、シネ・ヌーヴォ、京都みなみ会館、ほかにて上映中!
山本英、冨永昌敬、竹内里紗、宮崎大祐、清原惟 5人の監督が紡ぐ
YAMATOから生まれた5つのストーリー
豊かな自然も特徴的な街並みも産業もない日本のどこにでもある街YAMATO
当たり前の人々の当たり前の暮らしが風景につけた小さな滲みが、今、世界に向けて広がり出す
2021年/ 16:9/ 5.1ch./ 120分
企画:DEEP END PICTURES/製作:大和市イベント観光協会/配給:boid/Voice Of Ghost (C)踊りたい監督たちの会
https://voiceofghost.com/archives/category/made-in-yamato

スズキナオ:
まずは大和のことをお聞きしたいです。宮崎さんはいつから大和に住んでるんですか?
宮崎大祐:
母の本家がある大和を本拠地にして、父の仕事の都合で中学生ぐらいまで関西、川を挟んだ横浜側、海外とかいろんなところに移り住んでいたんですけど、高校の頭ぐらいから完全に大和に根を下ろしたというか、それ以降ずっと大和にいます。成人してから何か所か一時的に移り住んだりしつつ、基本的には大和っていう感じですね。
スズキ:
そうなんですね。根を下ろしているぐらいだから、いろいろと愛憎入り混じるのかもしれませんが、「大和にはなにもない」って宮崎さんは常にインタビューとかで話されていて、もちろん愛着はあるんですよね?
宮崎:
変わった街とか、歴史がある街とか、興味深い街の出身の作家がすごく多いのは正直羨ましくて。大和の場合は、無印良品のベッドのような無味無臭な記号的な場所に戻るみたいなイメージがやっぱりあって。大和だからどうとかってほんとに考えたことはなくて、ただ寝に帰る場所でした。
スズキ:
今回、ご自分以外のたくさんの監督が大和を舞台にした映画を作ったわけですが、それを宮崎さんがご覧になってどうですか?
宮崎:
それだけ何もないところをどう撮るかっていうことを自分はすごくあがいてきて、なんとなくそのコツがわかってきたので、今回皆さんに委ねたんです。どんなことをその自分の無印良品のベッドでやってくれるのかっていう楽しみもありました。例えば清原さんの作品に出てくる新幹線とか。ずっと飛行機の音はしてるけど、慣れすぎてて気づかなかったっていうのが、僕の昔の映画のモチーフのひとつで。毎日散歩しているうちに新幹線とすれ違ってるんだけど、新幹線がうるさすぎて早すぎて気づかなかったっていうことを、清原さんが映画化してくれたのはすごく嬉しかったです。早速パクって、僕の最近の短編に導入したんですけど、新幹線を(笑)。
スズキ:
当たり前すぎてという。
宮崎:
そういう普段気づかないようなことに目を凝らして映画にしてくというのが、この数年間の僕の作業だったような気もします。
スズキ:
この映画を観るとロケ地に行ってみたくなります。喫茶フロリダも行ってみたいし、太古レストランも。あれはどういう場所なんですか?
宮崎:
お金持ちの地主の一族の方がジュラシックパークに出てた恐竜を買い取って、自宅の庭の格納庫を建ててその恐竜を収蔵して、太古レストランにしたという。
スズキ:
昔からある場所なんですか?
宮崎:
10年ぐらい前からあって。コロナもあったし潰れちゃうんじゃないかと思って撮りに行ったら、そのオーナーはむしろコロナになって、皆さんエンターテイメントを求めてるから売り上げが増えましたみたいなことをおっしゃってました。
スズキ:
実際に行くつもりで検索してみたら、ポイントを貯めたらあの映画に出てきた動く恐竜に乗れたり、平日だとちょっとお得とか、いろいろあるようでした(笑)。
宮崎:
なんか盛り上がってるらしいですよ。僕は撮影で初めて踏み入れて、料理も食べれてないです(笑)。

スズキ:
今回の宮崎さんの作品のなかに、セブンイレブンとかUber Eatsを真っ先に始めたデニーズとか、なんでもないような場所がふたりの思い出の場所として出てくるじゃないですか。あの感じに僕はすごい共感を覚えたんです。ちょっと自分の話になってしまうんですが、大阪に引っ越してくる8年ほど前まで東京の豊島区に住んでいて、割と閑静な住宅街が広がってるような場所だったんですよ。なにもないなと思ってたんですけど、自分がライター活動をしようかと思っていた頃だったのもあって、例えば近所の中華料理屋に思い切って入ってみると意外と人がいたりして、ラーメン美味しいなと思ったりとか。そういう場所でも、そこに子どもの頃から住んでいた友達と一緒に歩いてると、「この公園で中学の頃よく溜まってた」とか、そういうのを案内してもらって歩くとなんでもない場所に見えても、まあ結構なんかあるっていう。別のレイヤーみたいなのが見えてくるのが楽しくて、そういうことを文章に書いてきたりしたもので。それに近いなと。
宮崎:
それはスズキさんと今日お話するとなった時に、そこはもう完全に一致するなと。たぶん今の時代って大袈裟なこととかはあんまりお金もなくてできないし、人が見てぱっと驚くような分かりやすいものって映画にほとんど映されちゃっているので。だから翻って、部屋の中でなんかお互いの腹の内を暴き合うみたいな映画がとても多いと思うんです。でも、映画の可能性はそれだけじゃなくて、目に入ってるんだけど気づかなかったものにどうアプローチするかってこと。まさにスズキさんの文章でやられてるようなことと同じようなことを僕は割と考えていて、こんなの映画にならないよっていうところが映画になる瞬間みたいなのがとても楽しいというか。
スズキ:
だから、きっと大和をずっと撮られ続けているんですね。なにもないと言いつつも。
宮崎:
ある種の足かせではあると思うので、その足かせに抗う楽しみはあるなと思いつつ。明らかに面白いロケ地とか出されると、どこも撮れちゃうんでどこ撮っていいかわかんなくなっちゃうっていう逆の問題が発生しますね。
スズキ:
それが逆転してる感じというか、割となんでもない場所だけど、それがふたりには豊かな場所、つまんなさも含めて愛してる場所として出る。あと、「1年後に運命の人と出会うモス」ってセリフが、急に未来からの発言みたいでびっくりしたんです。
宮崎:
その1人称の自分を呼ぶ方法もそうですけど、時系列とか性別でとかと見飽きた世界の中でどんどん崩壊してって読み直されてくみたいなことをテーマとしてはやりたくて。だから、動物すら話し始めるし。
スズキ:
そうだ、猫が急に喋り出すという(笑)。
宮崎:
そういう世界に最近ちょっと意識がありまして。今が現在なのか、未来がひょっとしたら懐かしいものなのかもしれないし、過去が新しいものかもしれないって森山大道じゃないですけど、いろんなものの境界が今自分が感知してるこの1点に集まってきちゃうみたいな世界を映画でやることが最近マイブームではあります。
スズキ:
随所に「俺」とか、「わい」とか、「僕」とか一人称の揺れがあって。あと「ゲロゲロ」っていう言葉も自分の世代的には——
宮崎:
80s感が。
スズキ:
そうです、そうです。「ぴえん」と「ゲロゲロ」が並列にセリフとして登場する感じとか、そういうような揺さぶられポイントがいろんなところにあるなと。タイムカプセルを埋めるのも、恐竜が周りにいるレストランで会話してるのも、時代感が揺さぶられて、昔なのか未来なのかわかんなくなる感じがあって。
宮崎:
最初のシーンも音とかで、宇宙船の中みたいな処理を施していて。ダイナソーレストランの中もそうなんですけど。宇宙船の中で未来人だか宇宙人が過去の人間を再現してるように見えなくもないとか。どの辺に自分がいるのか、よく定まらない感じの映像と音みたいなのをイメージしてました。
スズキ:
音作りについても聞きたくて、最初の一音めのギターの音が、こんな音が出そうっていうイメージと違いすぎてショッキングで。ぐにゃ〜んみたいな(笑)。あれはどういう感じで?
宮崎:
この映画を撮った頃によくメタルを聴いていて、元々メタルがすごい好きなんですけど、なぜかラップ好きみたいなキャラづけをされていて。メタルの中でドゥームメタルっていうすごいゆっくりしてってるメタルみたいなのがあるんですけど、それにはまってたので、それを主人公たちが演奏してるという設定で、実際あのふたりと下北のスタジオに行って練習したりとかしました。でも、思ったような音が出てなかったので後からプロのドゥームメタルのギタリストを呼んで、その人に合わせて演奏してもらってはめました。
スズキ:
それであの音になってるのか。すごくそこに労力をかけられてる。
宮崎:
そこに予算と労力が9割方かけられてるという(笑)。ガラケーだったのを、あのカット撮るためにiPhoneを初めて買ったし。ギターとアンプを買って、衣装も買って、それで予算のほぼなにもなくなってしまったので、あのワンカットにかけてたんですけど、意外とあっさり終わるので悲しい気持ちにもなりました。

スズキ:
いやいや、結構掴まれたというか。あと、これも揺さぶりの1つだと思うんですけれど、最後に出てくる「モトナリ」とそっくりの「モトノリ」とか。「モトナリ」に電話をかけているはずなのにその本人から電話がかかってきて、不安になる感じとか。
宮崎:
次元がいろいろあるみたいなのがイメージとしてあって。最近、自分の左目が割と青く世界を見ていて、右目が黄色く見ていて、病気なんじゃないかと思って病院に行ったら、病気じゃなかったんですけど。ちょっと疲れてるから青っぽく世界を見ようとかモードを切り替えるときに使い分けたりしていて。その経験とか、視点がずれるのが子供の頃から気になってたんで、それをいつか映画にしたいなと。こんな感じのちょっと坂元裕二みたいな、小気味良いセリフとその認識を融合してみました。
スズキ:
いい発見はある(笑)。しかも、あれがこの映画全体のことも象徴してるっていうか。いろんな視点で大和が捉えられて、どれも別に正解とかではない。私の見てる世界かどうであるかは、他人にはわからないですよね。
宮崎:
いろんな眼差しとか、例えば、人間に似てるような眼というのが世界中にいろいろあって、それが一緒にあるという状態を映画にしたくて。どっちが犯人ですか? こいつでした、じゃじゃーん!みたいなことに映画の役目というのはないと思うので。世界にそれだけの認識とか眼差しがあるっていうことを見せていきたいモードになっています。
スズキ:
映画を観て現実が不安に思えてくるのとかも、映画の面白さですよね。
宮崎:
自分が今見てる世界と、また全然違う世界が並走してたりとか、底に沈んでたりとか。そう考えると、なんか怖くもあるけど、すごく楽しいというか、胸がワクワクする感じもあったりして。
スズキ:
『MADE IN YAMATO』は宮崎さんの作品だけじゃなくて、全体的に不穏だったり、不安だったり、どう着地するのかわからないみたいな感じもありますね。
宮崎:
話がしっかりまとまるものとか、結論が出るような映画を元々撮る方々ではなくて、映画をきっかけに観た人のなにかが変わるような映画を作られるので、そうなるだろうとは思ってました。でもやっぱり、コロナの当時の深刻な状況っていうのは、なにかしら影を落としてるのかなと。もうこれがひょっとしたら、自分が撮る最後の映画になっちゃう、なっちゃったらどうしようとか。いっぱいのクルーが照明を焚いてとか、いわゆる映画の撮影がもうできなくなっちゃうかもしれない場合に、私たちはどう映画を撮ってったらいいんだろうと、たぶん全員が思ってたんだと。そういうものが、なんか深層心理的に反映されたのかなという気もします。
スズキ:
話が飛び飛びになってしまうんですが、宮崎さんの映画って女性ふたりのペアが多くて、男性は結構ひ弱な人が出てくるという印象を受けるのですが、それはなにかあるんですか?
宮崎:
まず男性に関しては、たぶん自分が弱いからだし、僕の知ってる男性たちもほぼみんな弱くて、幼稚で虚勢だけ張って筋力だけ発達してるというタイプで。
スズキ:
いいとこなし(笑)
宮崎:
でも優しいし、そういう人たちも確実に存在していて、そういう人たちを受け入れるべきなのが世界であり人間だと。女性は僕にとってみんな圧倒的他者で、性別が違うとかいうレベルを超えた距離を僕はいつも感じていて。その人たちが映画に出てくれて言葉が通じるって、ちょっと極端な言い方をするとすごい変わった特殊な動物が、自分の映画に映ってるぐらいの認識なんですよ。そういう人たちが映画の時間のなかでまた新しいなにかに変化する瞬間に興味があったので、今まではそういう思想の実践としての撮り方をしてたと思うんです。最近はもうそれすらなくなって、周りの人間全員がそれぞれに特殊な動物で、映画の中でどう変わるのかということに興味が移行しつつあるので、ひょっとしたらこれが最後の女性ふたり組み映画。次からはもっと男性も、いずれも弱いんですけど、出てくるだろうという予感がしています。あと自分の内面が割と女性的ななにか、絶対女性ではないんですけど、2組の女性的なイメージのようなものでできてるような気がしていて。それが双子っぽいものなのかわかんなくて、まだ明確には言語化できてないですが。最初の話のロジックで女性を撮ってきてたんですけど、それだけじゃないなにかを最近考えていますね。
スズキ:
面白いですね。ふたりの関係もめちゃくちゃ親友っぽいかと思えば、お互い知らない部分もすごくあってという感じで。
宮崎:
なんとなく周りの雰囲気で友人だとか、恋人だとか、家族だとかに設定されてるだけで、よくわかんないしすごくよくわかるし、大好きだけどすごく嫌いで、私とその人との間にだけ存在するなにかで繋がってきてるはずで。でもなぜか経済的というか、情報処理しやすい関係性に名付けられちゃうだけで、そうじゃないものをそのまま映画に持ち込みたいというのが強いんです。
スズキ:
その映画の中に映ってるふたりの関係性は、どこらへんまで宮崎さんが演出をされるんですか?
宮崎:
結構細かくキャストの方々とやっています。こういうことですよね?って決めて一方に流れていきそうになると否定して、ちょっとずらして、何者にも寄りつかない、名付けられない状態を撮影の間も準備の段階でもつくっていくことをします。
スズキ:
そうなんですね。すごく自然に振る舞っているようなふたりに見えますね。
宮崎:
落ち着かない状態が自然に見える状態を作るって、ちょっと言い方は変なんですけど、そういうイメージで普段は演出をします。その日にいきなり来てやったっぽいんですけど、めちゃくちゃ練習して、とんでもない時間をかけてやってたりとか。人によるんです。いきなり来てやれる人もいるんですけど。演出と演技と人間って面白いなと思います。
スズキ:
愚問かもしれないんですけど、映画を作る上で短編の短さなりの面白さもあるんですか?
宮崎:
僕は結構、短編が不得意なんです。なんかぐちぐちと長々言いたくなっちゃう人間なんで、さくっと終わると自分もモヤモヤしちゃうんです。だから、なるべく撮らないようにしたんですけど、ここ数年はコロナもあって、短編でできることを試みようっていう時期ではあったんです。
スズキ:
今、制作中のものはあるんですか?
宮崎:
来月に珍しくティーンエイジャーの男の子と女の子の成長を描いた映画を予定しています。
スズキ:
じゃあまたちょっと違った一面が見られると。
宮崎:
最初に台本を送った時に、キャストの子たちから、これ宮崎さんの映画ですか?って聞かれたぐらいに、全然イメージが違うらしく。「好きだー!」みたいなシーンが結構多い(笑)。
スズキ:
楽しみですね。あっという間に時間が経ってしまいました。
山﨑支配人:
スズキナオさんの今後のご活動予定は?
スズキ:
集英社新書で『それからの大阪』という本が出ていまして。僕が大阪に越してきて8年になるんですけど、あちこち町を歩いたり、人に会ったりして書いたものをまとめた本です。
宮崎:
なんか近いんですよ、たぶん、というのを最後に言いたいです。
スズキ:
年齢も近いし。
宮崎:
年齢もほぼ一緒で。そういったものを切り取ってどうにか物語にするというか、残していく姿勢というのは勝手に共感していました。
スズキ:
嬉しいです。大和にも近いうちに行く予定を立てているところなので、いろいろと案内してください。
